はじめに
日本人のソウルフードカレーライス。カレーは元々インド発祥の料理ですが、それに白米を付け合せたカレーライスは日本独自の料理となっています。外を歩いていて「あー!カレーライスが食べたい」となったとき、一番に思い浮かぶのは「ココイチ」ではないでしょうか?
カレーライスを専門的に取り扱っているチェーン店というと他に中々思い浮かびませんよね。これは皆さんが様々なお店を知らないという訳ではないのです。実際にココイチ以外のカレーライスチェーン店はほとんどなく、カレーライス市場はほとんどココイチの独占状態であるからなのです!それではなぜ、ココイチは他店をここまで圧倒するほど拡大することが出来たのでしょうか。
80%という圧倒的なシェア率!カレー界の王様「ココイチ」
ココイチの店舗数は国内海外合算して1395店となっています(2015年3月末)。それに対して、次に続く「ゴーゴーカレー」や「カレーのチャンピオン」の出店数は70店舗ほどです。つまり外食カレー業界におけるココイチのシェアの高さは圧倒的であるということが分かりますよね。数字にして80%を超えるシェアとなっています。これこそ私たちが「外でカレーを食べる」=「ココイチ」の図式を思い浮べる理由なのでしょう。
他のカレーショップが「ココイチ」に勝てない4つのワケ
1. ココイチの特徴は「特徴が無いこと」

このカレー業界でココイチ一強という状況の要因を、カレー総合研究所の井上岳久さんは特徴がないことだと分析しています。
カレーはつい隠し味を足したり香りに深みを加えたりと“足し算のカレー”にしてしまいがちです。しかし味の好き嫌いが激しい食べ物なので、特徴をつけ過ぎると敬遠されてしまいます。そこが難しいところなんです。その点、ココイチは“引き算のカレー”で尖った部分はないけれど、万人に親しみやすい味に仕上げています。言ってみれば目立たないけれど皆に好かれていて、生徒会長に立候補すれば確実に当選する――そんな優等生的な存在です。
(出典:カレー専門店 シェア8割の絶対王者ココイチはなぜ強いのか|NEWSポストセブン)
確かにスーパーなどに行ってカレールーのコーナーに向かうと様々な種類のカレールーが売られていますよね。カレールーの好みは人それぞれで、よく口にするものであるゆえにそのこだわりも強い人が多いのではないかと思います。そこでこの”人それぞれの好み”の共通項をあぶり出し「特徴がない」ことを極めたカレーこそがココイチなのです。その結果、私たちの期待を裏切ることのない「王道のカレー」としてその地位に深く腰を据えることに成功したのです。
2. 自分の理想のカレー=「マイカレー」の魅力
しかし単に「特徴がない」ことを極めただけではどこでも食べられるカレーにしかならず、ファンは増えていきませんよね。ココイチのカレーがファンを増やし続けるワケは特徴のなさ以外に「マイカレー」戦略が挙げられます。ココイチのカレーで最も安いのはポークカレーで430円。このポークカレー、量は多くなく具もほとんどない。これだけではほとんどのお客さんが満足出来ないだろうと思われます。そこで自分好みのルーに変更したり、好きなトッピングを追加したりすることが出来ます。

これによりお客さんそれぞれの好みに合わせたカレーが完成されていき、「特徴のない」カレーは「お客さんそれぞれの好みを持つ」カレーへと変貌していくのです。もちろんルーの変更やトッピングには当然それ相応の追加料金が必要となります。平均すると客単価は850円程で、たくさんのトッピングするお客さんは1000円を超えることはざらではないそうです。しかし理想のカレーとなった「マイカレー」はお客さんの手を離しません!高くても買う価値のある自分好みのカレーが目の前にはあるのです。
そもそも他のカレーショップとはその商品の在り方が違います。ゴーゴーカレーやカレーのチャンピオン等、その他のカレーショップは自分のお店のオリジナルのカレーを売り込んでいくスタイルです。それに対してココイチのカレーは自分のお店オリジナルのカレーはほとんどなく、むしろお客さんに自分好みのカレーを作っていただくスタイルなのです。そのため独自路線を進むココイチに敵はおらず、巨大な競争相手は存在しないのである。
(出典:【CoCo壱番屋】海外でも強いカレーライス企業の戦略|YOUをつなく~個人と世界が関わる時代~)
3. 独自ののれん分け制度でフランチャイズ展開
大きな競争相手のいないことだけが強みではありません。ココイチを運営する壱番屋では独自のフランチャイズを展開しています。フランチャイズとは一般的に、すでに事業展開に成功している企業が「うちのマネをしていいよ」と他の企業ないし個人に資本や情報を売却することです。フランチャイズといえば資本だけを売り1ヶ月弱の研修を終えた後は各店舗にお任せといったものが多いですが、ココイチではフランチャイズ店舗にも2~5年の研修を要するのです。また「将来独立してフランチャイズ店を持つ候補の社員」として周囲の社員の認知の下、様々な場所にあるココイチの中で10店舗ほどを研修で回ることになります。

ここにココイチのフランチャイズの強みがあるのです。簡単にフランチャイズを任せるのではなく、フランチャイズ店舗にもきちんとした指導を行っています。そのためココイチはフランチャイズと本社との結びつきが強いことでも有名です。フランチャイズにも手厚い研修を行うためフランチャイズ展開の速度は遅く店舗数拡大には少々時間が掛かるようですが、ココイチの強い地盤を確実に広げてられているのです。
(出典:一人勝ちココイチの秘密…ルーはハウス、値下げなし、独特FC|ライブドアニュース)
4. 信頼があるから価格競争をしない
他のカレーショップも様々な施策を凝らしています。牛丼業界では「250円戦争」が勃発し、過激な価格競争によって客単価が下がる懸念などがある中、カレーショップ「ココイチ」は慄然と微動だにしません。他のカレーショップなどまるで目に入らないかのようです。
ココイチは創業してから長年値下げをしてきませんでした。値下げは「禁断の果実」であることを分かっているからです。値下げをして、一時的にお客さんを集めることは出来てもそれは短期的な措置であり、長期的に見ればマイナスの一途を辿ることになるのは目に見えています。「値下げをしないこと」それにはお客さんとの強力な信頼関係が大前提になります。

多少値段が高くても「おいしいものを提供してくれるだろう」という信頼をお客さんから勝ち得なくてはなりません。それに応えられなければ当然お客さんの足は離れいきます。しかしココイチは常にお客さんの目線に立ち、価格に見合うカレーを提供してきました。今のカレーショップの相場が維持されているのは、ココイチが創業から長年お客さんの要望を応えられるよう質の向上に努めてきたからこそだと言えるでしょう。
(出典:一人勝ちココイチの秘密…ルーはハウス、値下げなし、独特FC|ライブドアニュース)
カレーだけじゃない!接客にも本気だった
フランチャイズの研修に力を入れているココイチ。そんなココイチでは従業員の教育にも熱心で、店舗のサービスレベルを上げるために「接客コンテスト」も実施されているようです。コンテストでは様々な接客シチュエーションの下でマニュアル通りに動けているか、そしてマニュアル以外にお客さんに合わせて十分な気遣いが出来ているか等が見られるようです。東北地方の接客コンテストで優勝した吉田沙織さんは次のようにコメントしています。
私は日頃から、壱番屋のモットーである「ニコニコ・キビキビ・ハキハキ」を常に意識して接客しています。その中でも特に自信があるのは”ニコニコ”笑顔の接客です。
(出典:ココイチレポート 株式会社壱番屋 第32期 株主通信)
まとめ
ココイチは他と競うのではなく、自らの強みを売り出してブランドを確立させたことに成功の要因があったと考えられるでしょう。その勢いは止まりそうにもありません。外で「カレーが食べたい」となったときの選択肢が、「まだまだ一択ではないかな?」と感じる人が多いのがその結果の表れではないのでしょうか。
他と同じことを後から追っているようでは常に勝つことは出来ません。人と同じ経験をして人をまねることも、もちろん成長に繋がります。しかしある地点までたどり着くと、まねるだけではなく自ら考え、自分の強みや新しい発想を押し出していかなくてはなりません。それは企業の戦略でもアルバイトとして働くことも同じようなことが言えますよね。自ら新しい領域を開拓することがモノやコトの飽和した現代社会には必要になるようです。

2014年11月からt-newsWebライターとして活動中。東京大学に在学中であり、大学では哲学について学んでいます。哲学と現代社会の繋がりを考え、その接点として道徳教育に関心があります。t-news以外の場でも執筆を行っており、現在はエピニオ(http://epinio.jp/)というメディアで教育について論じています。t-newsでは読者さんにとっての「働く」と「学ぶ」の重なりを増大させることを期待した記事を書いています。












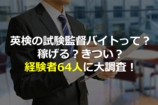

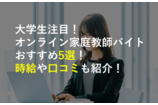




 人気バイトランキング
人気バイトランキング