- バイトあれこれ
- 2015/08/28
パソコンを使ったバイトをはじめよう!!ITバイト必須ツールを1から徹底解説
はじめに
プログラミングは勉強すれば誰でもできる!そしてそれが役に立つ!ということを以前の記事でお伝えしました。プログラミングを学ぶ中で手っ取り早いのは、IT系バイト(エンジニア、プログラマー)を始めることで、自らを成長しなければならない状況に身を置くことでしょう。でも、いきなり情報の世界に身を投じるのは怖いと思うかもしれません。そんなあなたに、IT系バイトを始める前に知っておきたい便利なツールを紹介します!
IT系バイトをやらないとしてもコンピュータを使うことは今後の社会でほとんど必須となっており、知っておくと色々捗ることでしょう。まさに、備えあれば憂いなしです。便利なIT系発祥ツールをぜひ使いこなせるようになりましょう!
これだけは使えるようになりたい!プログラミング必須系ツール
VMware || VirtualBox (仮想環境)
みなさんが普段パソコンで使っているOS(基本ソフト)はWindowsやMacだと思いますが、Webページを配信するサーバーやGoogleのスマートフォン用OSであるAndroidはLinuxと呼ばれるOSが基盤となっていることが多く、実際の開発現場でもLinuxが使えることが求められる場合が多いです。
Linuxとはフリーでオープンソースな基本ソフトとして全世界の開発者によって開発されており、主にサーバー用として用いられるOSです。有名なディストリビューション(導入する際のパッケージ)としてUbuntuやDebian, Fedoraなどがあります。

だからLinuxを普段から使える環境にあるということは、Linuxに慣れる上で大切なことでしょう。また最近はLinuxは商用OSに較べて遜色ない出来になりつつあり、インターネットやオフィスで文章を作るぶんには普段使いのコンピュータのOSをLinuxで置き換えてしまっても何も困らなくなってきています。
しかし、元から入っているWindowsやMacOSと共存させるには手間がかかり、最悪の場合データをすべてふっ飛ばしてしまうことにつながりかねません。だから、WindowsやMacOSの上にインストールできれば便利ですよね。しかしLinuxは基本ソフトであるゆえ、そのままではWindowsやMacOSと共存させて動かすことはできません。
そこでWindowsやMacOSの上に仮想的にコンピュータがあることにして、その上でLinuxが基本ソフトとして動くようにすれば、他のソフトと同じようにLinuxを扱うことができます。つまり、あたかもコンピュータがコンピュータの中で動いているように内部処理をして見せかけているのです。

このためには、VMwareやVirtualBoxとよばれる、仮想環境を構築するソフトウェアを自分のコンピュータ上にインストールして、そのソフトウェアにLinuxインストール用のCDやDVDデータを読み込ませます。そうすると、仮想環境の内部にある仮想DVDドライブがその中身を読み取り、内部に再現されたコンピューター上にLinuxをインストールすることができるのです。
どこで必要になるの?
Linuxは2014年現在、8割弱の大企業のサーバ、データセンターで導入が進んでおり、開発の現場ではWindowsよりLinuxを扱える技術者が求められています。LinuxやMacOSでしばしば使われる、キーボード入力でプログラムを操作するコマンドを使いこなせることが、プログラミングをはじめウェブ系の開発をするバイトやサーバー管理などでは重要であり、それに慣れておくことは大切でしょう。
参考ページ
http://www.vmware.com/jp
https://www.virtualbox.org/
Git && Github(バージョン管理)
プログラムを書いている中で、一人だけで開発しているとあまり気づかないことですが複数人で管理していると「過去に書いたプログラムコードを確認・復元したい!」「複数人で同じプロジェクトを平行して開発したい!」という場面が出てきます。そういった時、いちいちファイルを毎回バックアップしておくとか、ファイルの受け渡しをDropboxなどでしているのでは手間がかかるし、書き換えた場所がバッティングしてしまうことがあります。
こうなることを防ぐために、ファイルの変更点の履歴を保管しておき、いつでも、また複数人でもそこにアクセスして過去の情報を復元、また新しい情報を保存できるようなシステムが開発されてきました。こういったシステムを「バージョン管理システム」と呼びます。

最も有名なバージョン管理ツールは「Git」でしょう。さきに紹介したLinuxの開発でも用いられているほか、「Github」と呼ばれる、ソースコード(プログラミングをして書いたコンピュータへの命令文をこう呼びます)の共有サイトでもgitを用いたファイルの管理が行われています。
バージョン管理システムでは、「リポジトリ」と呼ばれるデータベースにファイルの変更履歴が保存されていて、githubはそのサーバーがオンライン上にあります。ユーザーはサーバーから最新のリポジトリをもってきて(プル)、自分のコンピュータでそれに変更を加え、履歴を登録(コミット)し、サーバーにアップロード(プッシュ)することで、新しいバージョンのソフトウェアを履歴に加えることができます。
もし複数の人が同じファイルの同じ位置に異なる変更を加えた場合、どうなるでしょうか。このときに勝手に上書きされてしまうのではなく、具体的にどのファイルで競合(コンフリクト)が発生しているかを教えてくれます。だからそのファイルの相違点を見比べて自分で変更履歴を統合(マージ)することで、複数の変更を適切に処理することができるのです。
どこで必要になるの?
多くのIT企業ではgitやsubversionといったバージョン管理ツールを用いてソースコードを管理していますので、プログラミングバイトをしたい人はその使い方に慣れておくことは大切でしょう。またherokuとよばれるサービスは、gitのリポジトリの形でサーバー上にファイルをアップロードすることで、そのリポジトリに登録されたWebアプリを実行してくれます。自分でWebサービスを作る際にも、gitの知識は必要不可欠といえますね。
参考ページ
https://github.com/
使いこなすと便利なエディタ・作業効率アップ系ツール
Atom(エディタ)
さてみなさんはプログラムを書くとき、どんなエディタを使うでしょうか。
統合開発環境(IDE)とよばれるエディタ・デバッガー・コンパイル・テストまで一括で行える高性能なソフトウェアもありますが、重かったり余分な機能がついていたりして使いにくいこともしばしばです。ちょっとしたコードを書いて動かしてみたいときや、スクリプト言語と呼ばれるPython, Rubyなどを実行したいときはIDEを使うまでもない場合がほとんどです。でも、Windows付属のメモ帳でコードを書くというのではわかりにくくて仕方ありません。
そこで今回紹介するのはさきに紹介したGithub社が開発しているAtomと呼ばれるエディタです。このエディタは他のプログラミング用エディタと同様に、コードハイライトと呼ばれる、プログラミング言語に応じてその言語の命令を色付けして分かりやすくしてくれる機能や行番号、フォルダツリーを表示してくれるという便利機能がついている上に、優れたUIで直観的に使える上、必要な機能をその都度プラグインの形でAtom上で導入できるので、その取捨選択も容易です。
UIとはユーザーインターフェースの略であり、ここではプログラム画面のデザインのことを指して用いています。最近はただ使えるソフトウェアより、UIが整っていてユーザーが使いやすいソフトウェアを開発することが求められています。
 たとえばGitを扱うための拡張ツールをプラグインとして導入することで、Atom上でcommitやpushといったリポジトリ操作までできるのです。
たとえばGitを扱うための拡張ツールをプラグインとして導入することで、Atom上でcommitやpushといったリポジトリ操作までできるのです。
プラグインとは、アプリケーションの機能を追加・拡張するために入れるプログラムのことで、「アドオン」などとも呼ばれます。Atomではpackageという名前で管理されています。
最初ダウンロードすると、メニューがすべて英語で焦るかもしれませんが、環境設定のところからpackagesで"japanese-menu"を導入することで、メニューが日本語化されますので英語が苦手で...という方でも心配せずに使いはじめることが可能です。次世代型エディタのはしりとなるAtom。今後もこういったタイプのソフトウェアが登場することが予想され、その発展には目が離せません。
エディタを自分好みにするというのはこれはプログラミングだけでなく、執筆を生業とする職種であれば誰でも役に立つtipsです。プログラミングでは自分に適したカスタマイズをしたエディタを使うことが開発の速度を向上しやりやすくしてくれます。「隗より始めよ」という諺にもあるように身近なところ、つまり環境構築から始めていきましょう。
参考ページ
https://atom.io/
Markdown記法(ノートをとろう)
ではさっそく、練習としてAtomを使って講義のノートを取ってみましょう。そのときに便利なのが、Markdown記法とよばれる書き方です。Firefoxを使っているのならば、Ctrl+U キーを押してみましょう。するとこのホームページのソースコードを見ることができますが、見出しは<h1></h1>といったタグで囲まれています。
こういったhtmlファイルをブラウザが、「h1で囲まれた部分は見出しだ」と判断して大きい太字にして表示するようにしている、というのがネイティブな実装です。こういったタグで囲む書き方をMarkup記法といいますが、もっと見出しや太字の部分を分かりやすく書き表せないか、ということで登場したのがMarkdown記法とよばれる書き方です。
Markdownの書き方は比較的容易です。大見出しにしたい行の冒頭は"#"、中見出しは"##"、などと"#"を見出しのレベルに応じた数だけ書けばよく、他にも、太字にしたかったら**と**で挟めばよいのです。そうした後これをhtmlファイルとして出力すれば、任意のブラウザで開ける自動で整形されたノートが作れるのです。
この書き方ははてなブログやQiitaと呼ばれるプログラミング情報共有サイトでも用いられる記法なので、「技術ブログを作って自分の学んだことや、やっていることを周囲に発信したい!」と考えている方にはぜひ習得してもらいたいと思います。そういった技術ブログを持っていると面接でアピールできると、企業側も応募者がどういったスキルを持っているかを予め把握することができるので、優位に立てるといえそうですね。
Qiitaは、プログラミングに関する知識を記録・共有することを目的として作られたwebサイトで、自分がプログラミングや環境構築をする中で得られた知見を誰でも投稿・閲覧することができるサービスです。
どこで必要になるの?
最近はエンジニア系インターンの選考でも、応募者のプロダクトやgithubのリポジトリを企業のプログラマがみて面接に呼ぶか決める例があり、そのためには自らの成果や学習事項を発信できるようになっておくとよいでしょう。その際、マークダウン記法は執筆をスムーズにする潤滑油として作用することでしょう。
参考ページ
http://qiita.com/Qiita/items/c686397e4a0f4f11683d
https://qiita.com/
まとめ
IT系バイトを始める前に知っておきたい必須ツール紹介、いかがでしたでしょうか。開発を始めるとなると面倒なことも多いのですが、ストレスなく開発が進められるようにさまざまなツールがあるのです。これらのツールも使い方に慣れるまでは若干の手間を要しますが、使いこなせるようになると便利ですし、企業でもそういったツールが使える人は即戦力として重宝されることでしょう。こういったツールを知った上でITバイトに応募してみてはいかがでしょうか。

t-newsWebライターを2015年3月から始めました。
現在は都内の大学で3年生をやっています。理系の視点から『働く』ということに着目した記事を発信していきたいと思います。趣味は読書と映画鑑賞。座右の銘は「なせばなる」です。昨日の自分よりも少しでも進化した今日の自分でありたいと思っています。よろしくお願いします。










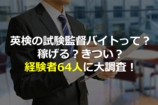

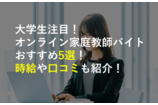




 人気バイトランキング
人気バイトランキング