- 2013/08/30
なぜ増える!? 64=65の不思議!!
64=65?
まずは下の画像をご覧ください。

上の図形は縦横の長さがともに8の正方形で、それをA,B,C,Dの4部分に分割します。
さらにそれを組み合わせたのが下の図形。
下の図形は縦の長さが5、横の長さが13の長方形です。
ここで、二つの図形の面積を計算してみると・・・
(上の図形の面積)=8×8=64
(下の図形の面積)=5×13=65
・・・あれっ?
上の図形を分割して、向きと位置を変えて組み合わせただけなのに、下の図形では・・・
面積が1増えてしまっています!!!!
なぜこんなことが起こる?
いったいどうして面積が増えるのでしょうか。きっとこの文章を読む頃には少しくたびれるほど頭をひねった方もいるかもしれません。分かってしまえば簡単なタネなのです。
これは先ほどの画像の下の図です。
この長方形の対角線に当たる、左斜め下に下りる線をよく見てみてください。
この線、実は直線ではないのです。
方眼を利用して傾きを数えてみたり、定規を当ててみたりすれば分かるかと思います。
あたかも二つの直角三角形によって作られているように見えるこの図形の真ん中には、実はわずかな隙間があります。それこそが、「増えた面積1」の正体だったというわけです。
この問題に大きく関わる、有名な「あの数列」
「フィボナッチ数列」を知っていますか?誰でも名前くらいは聞いたことがあるほど有名な数列かもしれません。フィボナッチ数列というのは、「0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,…」という具合に、前の二つの数字の和が、次の数字となる(1+2=3,2+3=5,3+5=8,5+8=13,…)ように作られた数列で、この数列に出てくる数のことをフィボナッチ数と呼びます。さて、お気付きでしょうか?先ほどの問題の図形で出てきた長さ(5,8,13)は、すべてフィボナッチ数なのです。
このフィボナッチ数、先ほどの問題とどんな関係にあるのでしょうか。 フィボナッチ数列にはある特徴があります。それはフィボナッチ数列において、「挟まれる数の2乗と、挟む2つの数の積の差が、常に1である」というものです。文字で書いてあっても少し分かりにくいですね。例えば、「…,5,8,13,…」と並んでいるので、(挟まれる数)=8,(挟む2つの数)=5,13 であり、8の2乗は64、5と13の積は65であることから、確かに差は1になることが分かる…ということです。この「差の1」が、先ほどの問題における「増えた面積1」にあたり、これを応用すれば、ものすごく大きな数字で先ほどの問題のような図形を作ることも出来ます。
いかがでしたでしょうか?
「直線に見えるけど実は違うだなんて、何だそりゃ!ただの目の錯覚じゃないか!」とがっかりした方もいるかもしれません。しかし、このような錯覚を作り出せるのは多いようで実はかなり少ない、フィボナッチ数によって作られた貴重なパターンだけなのです。数字の世界は非常に奥が深く、全く関係のなかった数字たちの間に思わぬ架け橋があったりするものなんです。それは現実世界でも同じこと。全く関係のないように思われる事柄に、意外な共通点を見つけることがあるんです!もしも何かに興味が湧くことがあったなら、とにかく調べてみてください。感動的な関係に出会うことがあるかもしれませんよ!
- 記事執筆:鈴木
- 都内の大学の経済学部に通っています。数学が好きです。










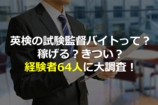
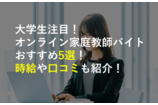





 人気バイトランキング
人気バイトランキング