<2023年3月更新>
一般教養はつまらない授業じゃない!
たいていの大学で必須科目の一般教養科目。東大生は1年は教養学部生として様々な分野の授業を受けますね。嫌々ながら受けてませんか?できるだけ楽な授業を探したりしてはいませんか?
今回t-newsでは東大生の皆さんに、自分にとって最も価値が高かった授業について教えていただきました。現役東大生の皆さんも、東大に興味がある皆さんも参考にしてみてくださいね。
1. 自分が変わることのできる授業
『工学部ゼミ』
実際に大学院の研究施設の行き、最先端の実験設備やソフトを使わせてもらえ、学業に対するモチベーションが上がりました。
(東京大学 理科1類 2年生 / 男性)
全学自由研究ゼミナール「見たい聞きたい伝えたい」
(担当教員名:立花隆)
ジャーナリストとして最前線で活躍されている立花隆氏が教壇に立ち、学生が自身の知的好奇心を頼りにジャーナリズム活動を行うという内容が、インプット主体の受験勉強から知的生産者としての大学以降の学問へと姿勢を転換するのにこの上なく優れた機会でした。集まってくる学生たちも優れた知性を持つ方ばかりで、東京大学に入学した甲斐があったと感じられる授業でした。
(東京大学 工学系研究科応用化学専攻 修士2年生 / 男性)
『大学ってなに?』
私が受けたのは、大学の意義とは何か?東大の教養科目の是非などを学生同士で議論させ、発表を行うゼミ形式の授業であった。大学自体に嫌気がさしていた当時の自分にとって、とても面白く主体的になれる議論であった。
(東京大学 工学部物理工学科 3年生 / 男性)
一般教養科目では多岐にわたった分野が扱われます。自分の専門分野外について知ることでモチベーションが上がったり、大学生の意義を感じたりするものです。また、自分の意外な得意分野が見つかったりすることもよくありますよ。
2. とても有意義な時間が過ごせる。
『科学史』
(担当教員名:橋本毅彦)
先生がとにかく情熱的であったからです。本来は学生は教師から多くのことを吸収し、教師は学生に少しでも多くのことを教える。それが指導のひとつのあり方だと私は思うのですが、科学史の先生は学生を一人の人間として扱ってくれ、毎回メッセージ性に溢れる講義をしてくださいました。あの講義を一年の初めに聴けて、大学に来てよかったと思いました。皆さんにもぜひお薦めしたい講義です。
(東京大学 医学部医学科 5年生以上 / 男性)
『中級英語』
英語でプレゼンする機会があったり、そもそも授業が英語で進められたりと通常の英語の授業と異なりとても刺激的であったし、英語を使うことに積極的になれ、大変有意義でした。
(東京大学 教養学部 2年生 / 男性)
『教育心理学』
理系の自分にとって興味はあるものの専門知識が皆無な心理学について、講師の方は例えも出しながら面白く講義を進めてくれた。教養がついたのみならず、次に興味を持つ分野も定まり有意義な講義であった。
(東京大学大学院 工学系研究科社会基盤学専攻 修士1年生 / 男性)
進振り後に学ぶ専門科目では学べないことが学べるのがこの教養科目の特徴。たいていは教授である先生の研究分野について講義がなされることが多いですが、やはり先生方も自分自身の得意分野を話すわけですから生き生きと授業されますよね。先生によってはかなり工夫を凝らす方もいるようです。
いろいろな先生の授業を聴いてみると、とても有意義な授業時間を作れそうですね。
3. 授業が独特
『認知脳科学』
(担当教員名:石金浩史)
ブレインマシンインターフェースなどといった工学系の先端技術を説明されたり、認知実験のVTR、レーシックや脳の手術の動画を鑑賞したり、さらには催眠術の実演など、とても興味深い内容ばかりの授業だったので。
(東京大学 教養学部 1年生 / 男性)
『囲碁で養う考える力』
囲碁は今までやったことがなく、機会があればやってみたいと思っていたのですが、新しいことをはじめるのは往々にして面倒であり、なかなか始めることができませんでした。この授業ではプロ棋士の方が教えに来てくださってみんな受講生は初心者なので気兼ねなくうてて、囲碁をよく学ぶことができ単位まで貰えるというととても良い授業でした
(東京大学 薬学部 3年生 / 女性)
『惑星地球科学実習』
(担当教員名:角和 善隆)
授業というと教室の中で完結してしまうものが多いように思われますが、この授業では、実際に伊豆大島などの行き、実地でいろいろなものを観察することができます。外でしか得られない経験を、ぜひ手にしてほしいです。
(東京大学 薬学部薬学科 4年生 / 男性)
同じ講義名であっても、大学によってその授業の内容はさまざま。かなりその大学の特色が出るといっても過言ではありません。東大もかなり興味深い授業があるようですね。いままで小中高と受けてきた授業とは違ってかなり体系的であったり、経験則に基づくものが多くなってくるのが大学の一般教養の特徴でもあります。今まで経験したことがないような種類の授業に出会えると良いですね。
まとめ
今回の記事はいかがだったでしょうか。一般教養の授業を受けられるというのは1年生の特権です。有名な先生の授業を聴いてみたり、自分の得意分野を伸ばす授業を受けてみたり。興味はあったけど教えてもらえる機会がなかった分野の授業を取ってみたり、視野を広げるため多角的に学問を学ぶために、今までまったく縁がなかった授業をとってみるとまた違った学生生活を楽しめそうですね。
関連リンク
サークルをやってて良かったと思う5つのこと
想定外!?意外とかかるサークルの出費
新歓だけではわからない!入部前後のサークルのギャップ
| 調査期間: 2013/10/18~2013/10/25 調査方法: WEBアンケート 調査対象: 現役大学生302人 性別内訳: 男性(47%)女性(53%) 学年別内訳: 1年生(46%)2年生(22%)3年生(12%)4年生(14%)修士1年(3%)修士2年(3%) |
- 執筆者;fuji
- 某国立大学工学部建築学科所属。現在博物館を設計中です。















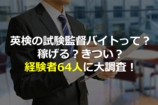
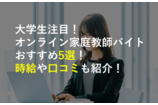



 人気バイトランキング
人気バイトランキング