世界で生きる教育推進支援財団の竹田さんにインタビュー
世界で生きる教育推進支援財団で働いている竹田さんに、お話を伺ってきました。この記事は後編です。
前編はこちら→【開成・東大卒の農林水産省職員が、霞ヶ関を飛び出した!】お役所より未知の教育界を選んだ訳とは
竹田 潤さん(以下敬称略)
開成高校→東京大学農学部卒
大学時代はバトミントンサークルに所属しながら、稲の研究に打ち込む。その後農林水産省に入省したが、ある出来事がきっかけで3年で退省し、現在は、経済的な理由によって国際バカロレアの教育を受けることができない子どもへの金銭的な支援を行う『世界で生きる教育推進支援財団』の運営に尽力している。
インタビュアー
石岡 佑梨 早稲田大学 文化構想学部2年
読んだ方々が、何か新たな発見をできるような記事を書いていきたいです。 趣味はチェロを弾くこととラーメン食べ歩きです。
国際バカロレアとの出会い
石岡:引き続きよろしくお願いします。農林水産省を辞められたあと、転職された先は最初からここ(世界で生きる教育推進支援財団)だったんですか
竹田:「いえ、まず若者支援をしているところとか、自分の出身校とか、いろんなところに行って、いろんな人にお会いして、自分のやりたいことを話しました。その最中で国際バカロレアの日本の委員をなさっている坪谷さん(※)という方と出会い、国際バカロレアの導入を推進する財団を一緒に作らないかと誘っていただいたんです」
(※)坪谷さんのインタビュー記事はこちら↓
前半【同級生の自殺から自分を見つめ直すためにアメリカへ!】私が経験した日本と世界の教育の違い
後半【もう国語算数理科社会の時代は終わった!?】インターナショナルスクールでの驚きの教育
石岡:ここで、国際バカロレアとはどのような教育法か、説明していただいてもよろしいですか
竹田:「国際バカロレアは海外で生まれた世界共通の教育プログラムです。学力も当然重視するんですが、コミュニケーションスキルや、相手の話を聞く力だったり、自分で考えて話す力だとか、いろんなスキルを伸ばすんです。学生の時にいろんなスキルを伸ばせるので、社会に貢献できるような人材が育っていくのです。しかし、国際バカロレアの教育を受けるためには、学校にも家庭にも少なからず経済的負担がかかることが、大きな課題です」
石岡:その、コストの課題の解決法は何かあるのでしょうか
竹田:「それが、当初坪谷さんに話していただいたアイディアの面白いところなんです。学校に民間の資本を入れて、民間の意見を取り入れたうえで国際バカロレアを導入するという方法なのです。私はそれに非常に共感したんです。なぜなら、経済界をはじめとした社会が教育に投資をすることで教育界がそれに合わせて変わっていくという仕組みが、いままで全くなかったんです。それができるかもと思い、それで坪谷さんと一緒に財団を創設することになりました」
石岡:竹田さんはいろんな人と会う中で、今の活動につながる方(坪谷さん)と出会うことができましたが、私たちが実りある出会いを生むために、心がけるべきことは何だと思いますか
竹田:「『こんなことやりたい』『こんなふうに社会に貢献したい』という目的を持つことだと思います。自分の目的を話すことで得られる意見や人脈があると思うんです。私は、いろんな人との出会いの中で『どの人と一緒に仕事がしたいのか』ということを考えていました。この人から学びたいと思えるような人と会ったときには、その人との関係をどんどん深めていくべきだと思います。出会って終わりだとすごく勿体無いですよ!」

教育の選択肢を広げる、国際バカロレア
石岡:では、竹田さんは今現在どのような内容のお仕事をされているのですか
竹田:「国際バカロレアは、学習指導要領外のものであるため、制度設計が非常に重要になってくるんです。基本的に役所でしか解決できないことなので文科省に通って、既存の学習指導要領との整合性や、外国人の先生が日本で働けるような免許制度の整備を進めてることが主な仕事です」
石岡:なるほど、竹田さんや経済界・教育界の力だけでは解決できない問題がたくさんあるんですね。他にも何かなさっていることはありますか
竹田:「国際バカロレアは認知度が非常に低いので、その導入の意義や重要性について、企業の方にご説明しております。あとはお母さま方の集まりでは、『今話題の教育、国際バカロレア』ということで非常に関心が高いので、そういうところにも伺って、活動内容を宣伝させてもらっています」
石岡:竹田さんにとって、今のお仕事の一番のやり甲斐はどこにありますか

竹田:「今まで誰もやってきてなくて、かつ必ずやらなきゃならない仕事をやっているということに、やりがいを感じますね。同じアジア圏の中国やインド、パキスタンなどは、国家プロジェクトのような形で国際バカロレアの導入を進めているんです。日本が世界から置いていかれるという状況の中で、『日本もそのような教育を取り入れていくべきだ』と思う方は多くても、それを実際に実行できる人はなかなかいないと思うんです。新しいことに取り組む際には、いろいろな苦労もあるんですけど、やりがいという面では、非常に大きいです」
石岡:今までやる人がいなかったという事実は、竹田さんにとって仕事のやりがいになっている一方で、他国と比べて日本の教育国際化が進んでいない現状の原因でもあると言えませんか
竹田:「そう言えると思いますね。ただ、国際化していないとは言っても、日本の教育も決して悪くはないんです。全国どこでもこれだけ質の高い教育を受けられる国はなかなかありませんし、世界でも日本の教育は賞賛されています。でもその教育に合う生徒も合わない生徒もいる。それだけで本当にいいのか、となってきたと思うんですね」

石岡:その課題への対策としてはどのようなものがあるのでしょうか
竹田:「日本の教育のいいところを保護しつつ、いろんな教育の要素を取り入れることが重要だと思います。例えば、国際バカロレア校が地域に一校、モデル校のような形で存在するということですね。そういった全く異質な教育をやっている学校が一つあるというだけでも、周りの学校はそこから学べることがあると思うんです。新しい教育の導入をフルにやらなくても十分効果は望める。日本の良さも残しつつ、新しい教育の多様な要素を取り入れていき、そのなかから、子供に合ったものを選択できるという形が理想的だと思います」
「自分を知る」ためにするべきこと
石岡:最後に大学生に向けて、何かメッセージをお願いします
竹田さん:「若いうちから、自分を知ることが大事だと思います。『自分はこういう方向に興味があるんだな』『こういうところが得意なんだな』とか、自分の中の興味関心を早いうちから発見できるといいですね」

石岡:それを発見するためのおすすめの方法はありますか
竹田:「ヨーロッパでは小中学生の頃からキャリア教育を受けて、自分にはどういう興味やスキルがあって、社会にはそれを生かせるこういう職業があるということを早い段階で学ぶんです。そしてそのキャリアを歩むためにはどういうことをすればいいのかという自分の方針が決まっていくんです。しかしながら日本にはあまりそういった仕組みがないので、ある程度自分自身で考えていかなければなりません。それが早ければ早いほど、そのあとの時間の使い方を、逆算して考えられると思うんです。例えば、1年生のときから農水省に入りたいと思えば、現場に行って農業の体験してみるとか、農業系の講義を取ってみるとか、いろんなことできますよね。最後に是非『教育を変えたい』や『国際バカロレアの教育って素敵』と感じてくれる方がいましたら連絡をいただければと思います」
石岡:本日はありがとうございました
前編はこちら→【開成・東大卒の農林水産省職員が、霞ヶ関を飛び出した!】お役所より未知の教育界を選んだ訳とは
竹田さんの活動はこちらから
国際バカロレア→http://www.ibo.org
世界で生きる教育推進支援財団→http://www.sekaideikiru.com/
世界で生きる教育推進支援財団
国際バカロレアは従来の教育に比べて、生徒に課される経済的負担が大きいものです。世界で生きる教育推進支援財団は、世帯の所得に応じた支援を行うことで、経済的な理由によって国際バカロレアを受けることを諦めることのないような社会を目指し活動しています。興味のある方は是非協力してみてはいかがでしょうか。











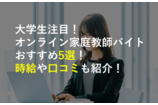



 人気バイトランキング
人気バイトランキング