<2023年3月更新>
複雑さ、高校の選択授業の比ではない
見知らぬ国へ行くと、往々にしてカルチャーショックを受けるのと同じように、大学の新入生は、高校までとは違った風習や制度に戸惑います。90分前後の講義、大教室、サークルの存在……。初学者である新入生を混乱させるのは、なにも法律や商業だけではないのです。特に、多くの大学に存在する履修登録という制度は複雑を極めます。高校の選択授業のように、いくつかある中からちょちょいと選んで、はい終了というわけにはいかないのです。何百と設置された授業のうち、学部学科によって受講できる授業は決まっており、受講できる中にも、必修、選択必修、選択、自由、など、様々なレベル分けがあります。さらには単位という尺度が導入された授業のシステムも、高校までとはかなり異なるものです。僕も、混沌としたこの制度を理解するのに苦しんだ記憶があります。また、どんな授業を選択すべきか、という実際の内容に関する難しい問題もあります。簡単なものをとるか、興味を優先するか……。しかし、先輩たちはみな、それぞれのやり方で、履修登録を克服しています。それについて実施したアンケートの集計結果を見てみましょう。
履修登録の道標
アンケートに示された興味深い事実は、履修登録の際に参考にしたものの1位は「学内冊子」であるのに、実際に一番役立ったものとしては「先輩からの意見」が4割近くを占めて1位、ということです。これは、思っていたよりも先輩のアドバイスが有効だ、ということを示していると考えられます。これに関しては後述します。
学内冊子も人気です。ここでいう学内冊子とは、実際に講義を履修・出席した学生たちにアンケートを実施して、授業の各種データを集計して発刊することで、履修登録に迷える子羊たちを救済しようというものです。質問項目は「授業形式は板書型か、レジュメ配布型か。成績評価は厳しいか、甘いか。定期テスト実施か、レポート提出か。講義内容は興味深いか、つまらないか」などがあります。多数意見をもとに編集されるため、偏見が比較的少なく、かつ網羅的であるという強力な利点があり、学生の評価の平均値ともいえるでしょう。その意味では「先輩からの意見」とは対照的かもしれません。東京大学の『逆評定』、早稲田大学の『マイルストーン』、慶應義塾大学の『リシュルート』などがその典型です。
他には、「友人との相談」や、大学が授業内容・評価基準等を公開する「シラバス」があげられていました。 一つ目の質問では、複数項目にチェックを入れた方が相当数おり、皆さんが様々なものを複合的に参考材料にしつつ履修を組んでいることがうかがえます。
先人の知恵に学べ
前述したとおり、実際の履修登録の際に役立ったと実感された1位の項目は「先輩からの意見」でした。実際の声を紹介しましょう。
先輩に聞くのが一番!入学したての一年生でも、サークルの新歓などに行けば、先輩が親身になって教えてくれるはず。利用しない手はありませんよ!
(一橋大学 社会学部 2年生 / 女性)
学内情報誌や先輩のアドバイスを参考にした方がよい。興味だけでとると、教授の授業がわかりにくい、教科書を自分で読んでいるのと変わらないといったことがある。
(早稲田大学 政治経済学部 1年生 / 男性)
シラバスを読むだけでは実際に面白い授業なのか分からない。先輩の評判を聞くと外れがなかった。楽に単位が取れる授業だけ履修すると、興味が沸かず授業に出る気もなくなってしまうので、多少厳しくても自分の興味のある科目を履修するといい。実生活に結びついている事が学べる授業を履修するととても勉強になる。
(慶應義塾大学 商学部 4年生 / 女性)
先輩からの意見を聞いたり、配られる冊子をよく読んで取る方がいいと思います。ただし授業名は同じでも担当教員が違うと内容や難易度が違う場合があるので、先生ごとに授業の様子をリサーチした方がいいと思います。
(京都大学 教育学部教育科学科 3年 / 女性)
実際に受けてみて、面白かったなり単位が取りやすいなど経験をした先輩から聞く情報が一番有用!複数人に聞くとさらに良いと思います。
(関西学院大学 社会学部 2年 / 男性)
先輩からどの先生がどういう授業を行ってどういう成績評価をしているのか、アドバイスをもらったことが参考になりました。
(大阪大学 工学部地球総合工学科 2年 / 女性)
サークル活動など一定の人間関係のある先輩からのアドバイスは、良くも悪くも主観的です。その先輩の考え方によって授業に対する評価が大きく揺れる反面、新入生の個々の希望や不安によく答えてくれるという利点もあります。サークルや部活などの新入生歓迎会では、先輩は親身になって履修相談に乗ってくれます。履修登録という制度そのものについてでもよいですし、どの授業が人気なのか、どのようなことに気をつければいいのか、など、わからないことはなんでも質問してみましょう。それをきっかけに新しい人間関係ができることも、あるかもしれません。
複眼をもとう
先輩は、新入生が尋ねれば、おすすめの授業をたくさん教えてくれます。学内雑誌にも、授業の評価が豊富に収載せれています。しかし、評価が高い授業の中には、高名な教授が開講している学術的におもしろい授業もあれば、単によい成績をとりやすい、成績評価が甘いというだけが勧める要因であるような授業まで、様々あります。勿論、単位取得が楽であることが悪であるということでは、ありません(東大の進振りなどでは、単位の取りやすさは死活問題になりえます)。むしろ、いくら心優しい先輩のアドバイスだからと言って、それを鵜呑みにするのは危険だ、ということです。大切なのは、自分の興味、先輩のアドバイス、学内冊子、シラバスなどを、どれもバランスよく見やりながら、情報を取捨選択していくことではないでしょうか。半年ないし一年間受ける授業なのですから、後悔しない選び方をしたいものです。
関連リンク
関心?楽さ?実用性?先輩たちが履修登録で重視したこと
悔いのない決断を。学部選びの動機になった3つの要素
本当にその言語でいいですか?気になる第二外国語のウワサ
ミスったら悲惨……!語学選択で重視すべきポイント
| 調査期間: 2013/01/02~2013/01/11 調査方法: WEBアンケート 調査対象: 現役大学生379人 性別内訳: 男性(42%)女性(58%) 学年別内訳: 1年生(44%)2年生(22%)3年生(12%)4年生(22%) 大学内訳: 早稲田大学(20%)慶應義塾大学(15%)一橋大学(5%)その他(60%) |
- 記事執筆:小松崎
t-newsの学生スタッフとして、記事作成を担当しています。 - 某大学の法学部生です。
- 最近は、様々な分野の本を乱読しています。















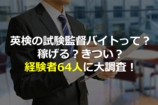
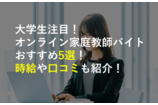



 人気バイトランキング
人気バイトランキング